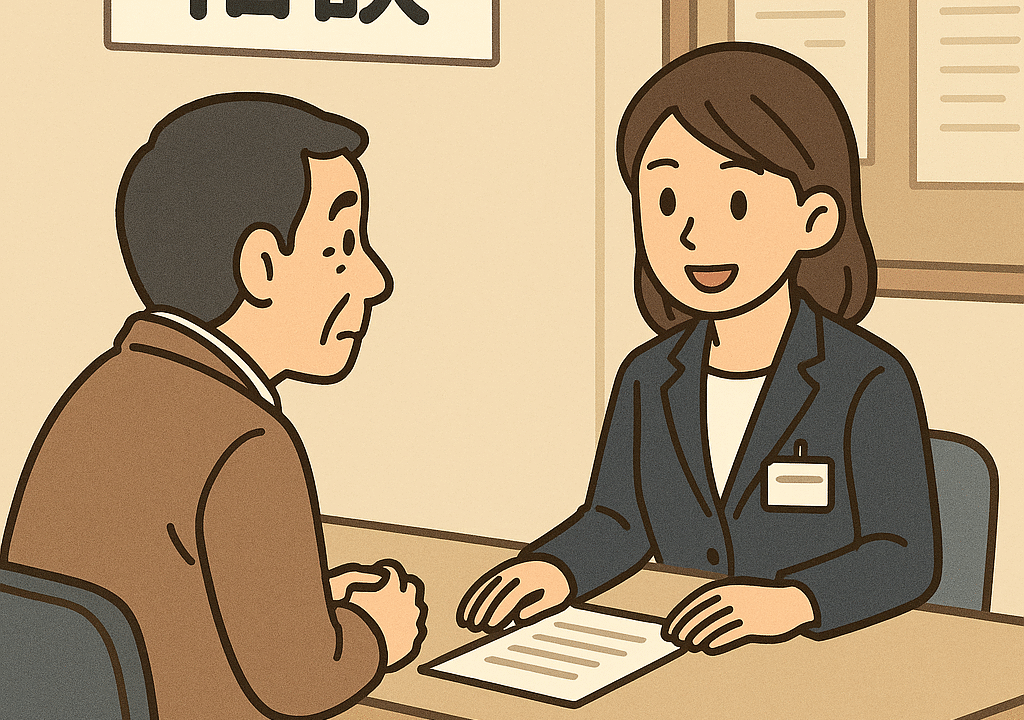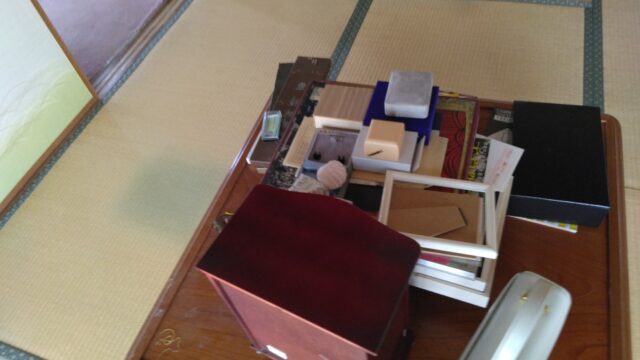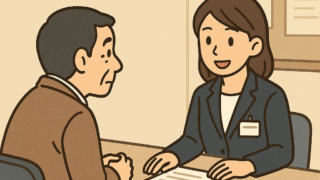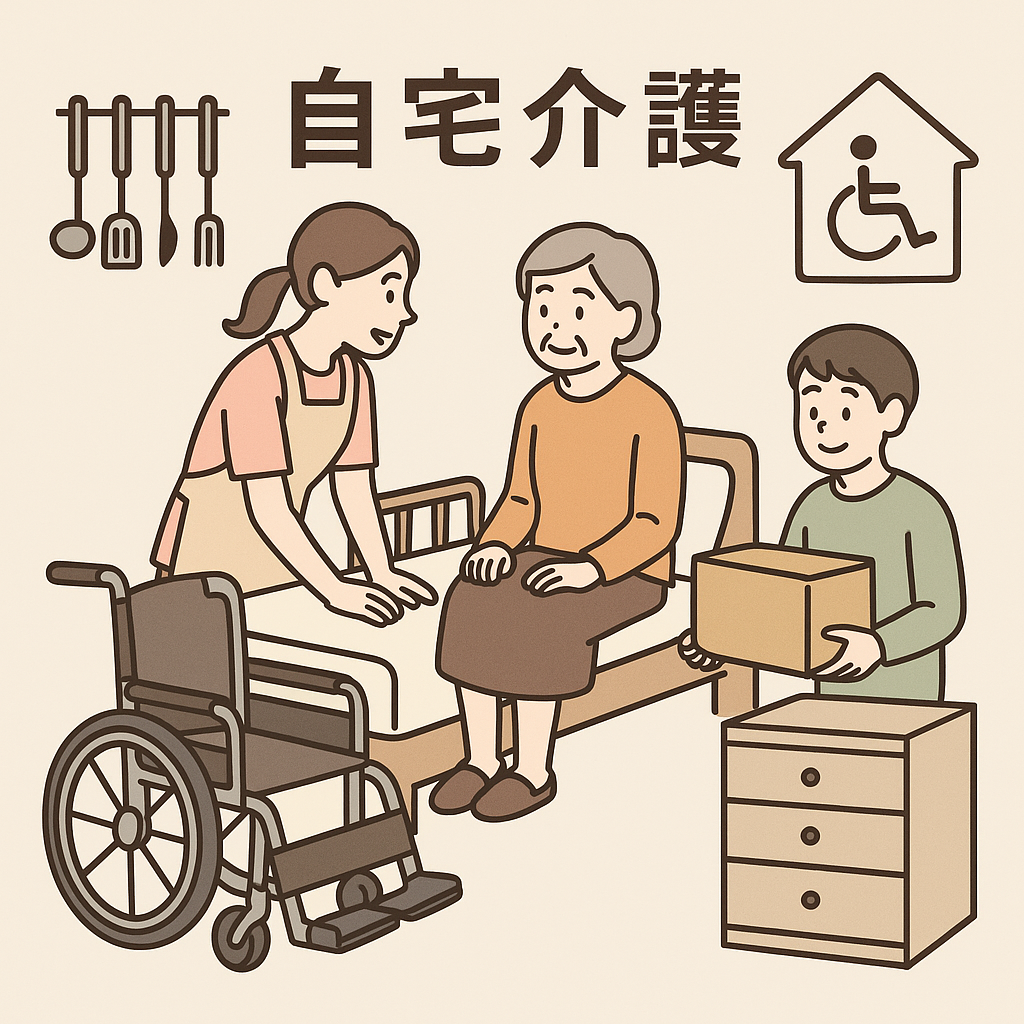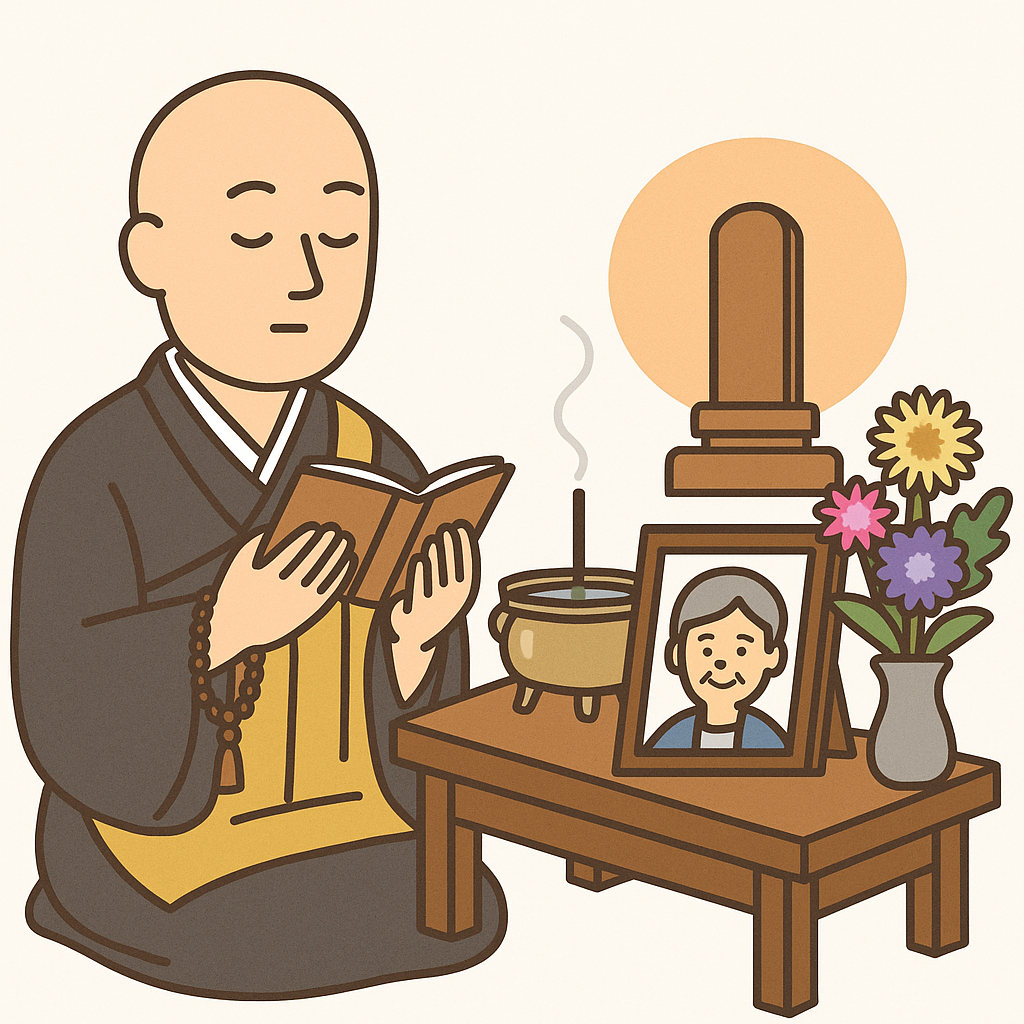「福祉事務所が遺品整理までしてくれるのでは?」──足立区でも、生活保護を受けていた方や一人暮らしの方が亡くなられたときに、こうした声がよく聞かれます。けれど実際には、役所の支援には限界があり、火葬や遺骨の保管は行われても、部屋に残った家財までは片付けてはくれません。では残された荷物や遺品は、誰が整理していくのでしょうか。本記事では、生活保護世帯や身寄りのない一人暮らしのケースを中心に、足立区の福祉事務所が「してくれること」「してくれないこと」を整理しながら、その後の対応の流れを考えていきます。
目次
福祉事務所が行う身寄りのない方の遺品整理について
一人暮らしの高齢者を支えるのは福祉事務所、と考える方は多いでしょう。では実際に、どこまで頼れるのでしょうか。生前は生活保護の申請や生活支援、見守りといった制度で日常を支えてくれます。しかし、亡くなった後はどうでしょうか。火葬や遺骨の保管といった最低限の対応に限られ、部屋に残った家財や遺品整理は制度の対象外です。結局のところ「誰が片付けるのか」という課題が残り、多くの方が戸惑う場面となっています。
身寄りがない、とは?
身寄りがないというのは、単に親族がいない場合だけを指すのではありません。ご親族が遺体の引き取りを拒否したり、相続を放棄した場合にも「身寄りがない」とみなされます。
生前に行われている支援のあらまし
- 見守り支援・相談支援
地域包括支援センターや民生委員と連携して、日常の相談や安否確認を行います。 - 介護保険サービスの利用調整
介護が必要になった場合、ケアマネジャーや介護サービス利用につなげます。 - 日常生活支援
食事や買い物、掃除などが難しい場合は「生活支援サービス」「ヘルパー派遣」などにつなぎます。 - 高齢者向け住宅・施設入所支援
住まいの確保が難しい方には、特養や有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などの入所を調整します。
身寄りがない方の亡くなられた後の対応
- 遺体の引き取り・火葬
ご遺族がいない、または引き取りを拒否した場合、市区町村が「行旅死亡人」として扱い、火葬を行います。 - 遺骨の保管と供養
役所が一定期間(多くは5年程度)遺骨を保管し、その後は「無縁仏」として合同墓地やお寺で合祀・供養されます。 - 遺品や家財の処理
基本的には役所が直接は行わず、大家さんや管理会社が処理します。
ただし、相談があれば福祉事務所が「どう進めるべきか」「どんな業者をあたるべきか」をアドバイスしたり、場合によっては3社見積もりを求めるなど調整に関わることもあります。
福祉事務所のサポートまとめ
- 福祉事務所は「生活保護の窓口」だけでなく、地域の高齢者やひとり暮らし世帯のセーフティネット全般を担っています。
- 生前は「見守り・介護・生活支援」を中心に、亡くなった後は「火葬・遺骨の保管」「無縁仏としての供養」まで最低限の保障を行います。
- 遺品や家財の処分は制度には含まれていませんが、大家や親族から相談を受けて、調整や助言をするケースはあります。
福祉事務所の生活保護の遺品整理の対応について
- 死亡時点で生活保護は打ち切り
→ 以降の費用は保護対象にならない。 - 葬祭扶助(火葬費用)のみ支給
→ 火葬や直葬が基本。
→ 遺骨は親族がいれば引き取り、いなければ役所が一時保管。
→ 多くの自治体では5年間保管後に「無縁仏」として合祀・供養。 - 部屋に残った家財・遺品について
- 福祉事務所や市町村が処分する制度はなし。
- 原則は 大家・管理会社・遺族 のいずれかが対応する。
- 遺族がいない/対応できない場合、大家が自費または敷金で処分手配。
- このときに、役所から「3社見積もりをとって業者を選定してください」と案内されるケースがある。 - 例外的な調整が行われるケースもある
- 福祉の担当者が、大家からの相談を受けて親族に働きかけることがある。
- 残っていた保護費(未使用分)を整理にあてられないか調整を行う場合もある。
- ただし制度として明確に定められているわけではなく、自治体ごと・担当者ごとに対応は異なる。
これに対してお身内の対応《一般的なケース》
1. まず知っておく原則
- 生活保護は死亡時点で終了します。
- 葬祭扶助(火葬費の補助)はありますが、遺品整理・家財処分は制度外です。
- 遺品=相続財産。原則、相続人(ご親族)が第一の責任者です。
- 相続放棄を検討中は、鍵の受領・処分・持ち出しは慎重に(単純承認に注意)。
2. 初動(0〜48時間):連絡と共有
- 福祉事務所(担当CW)/警察・医療機関/大家・管理会社へ事実共有。
- 鍵・所持品の引渡し経緯と担当者名・日時をメモ。
- 葬祭扶助の可否、遺骨の引取り・保管の段取りを確認。
- 室内は施錠と簡易換気など最小限の保全にとどめます。
3. 〜1週間:相続方針の決定と保全ルール
- 家族で承認/限定承認/放棄を検討。迷えば弁護士・司法書士等へ相談。
- 放棄の可能性がある間は、処分・売却・持ち出しをしない。
- 貴重品と重要書類の保全:現金・通帳・印鑑・身分証・保険証券・契約書・権利証などは
写真→簡易目録→封緘保管。 - 衛生・安全上の危険物(腐敗物・害虫源・強い悪臭)だけ最小限撤去。
その際は 写真・目録・領収書 を必ず残す。
4. 1〜2週間:仕分け・見積り・実施
- 遺品整理業者の見積りは複数(目安3社)。
比較ポイント:仕分け精度/処分内訳/養生・近隣配慮/買取可否/古物商の査定・証明書発行の有無。 - 作業時は第三者立会い(管理会社・専門業者・必要に応じて専門家)。
- 記録一式を保管:ビフォー/アフター写真・搬出リスト・処分領収書・査定証明書。
- 退去手続き:大家・管理会社と立会い→鍵返却→公共料金精算→賃貸解約を完了
一方で、例外的に「遺体の引き取りを拒否する」選択や、「相続放棄を行い遺品整理に関与しない」方法をとる場合もあります。引き取り拒否を選んだ場合は、自治体が公的に火葬を行いますが、後日扶養義務者として費用請求を受ける可能性もあるため注意が必要です。また、相続放棄を家庭裁判所に申述すれば遺産や債務の引き継ぎを避けられますが、期限内の手続きが求められます。
つまり一般的にはお身内が一定の役割を担う流れですが、経済的・心理的な負担が大きい場合には、法的手続きや自治体制度を利用して関与を最小限にとどめる選択肢も存在します。
当社へのお問合せ
家財整理センターは、賃貸物件の遺品整理・退去片付け・残置物撤去に20年以上携わってまいりました。専任担当者がご相談から作業完了まで一貫して対応し、立ち会いが難しい場合でも安心してお任せいただける仕組みを整えています。役所では処分できない品や、大家さん・管理会社とのやり取りも含めてサポート可能です。
ご相談・お見積りは無料で承っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ご利用の流れ
- お問い合わせ(電話・メール・フォームからお気軽に)
- お見積り(現地またはお電話で内容を確認)
- 作業開始(仕分け・搬出・お掃除まで)
- 完了確認(立ち会い、または写真でご確認)
初めての方でも安心してご依頼いただけるよう、シンプルで分かりやすい流れになっています。
お問い合わせはこちら
料金や作業内容についてのご相談は、下記よりお気軽にご連絡ください。
【 電話番号】全店共通 03-5860-6515